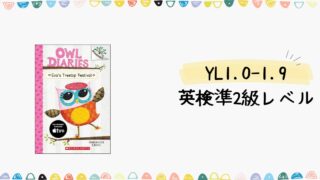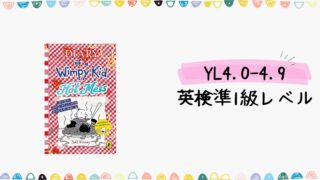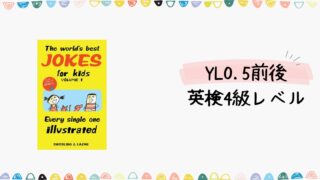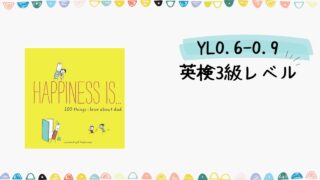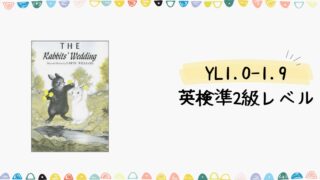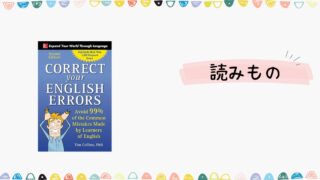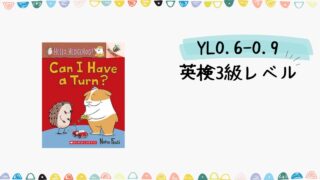 YL0.6-0.9
YL0.6-0.9 ACORN Hello, Hedgehog! シリーズ
Can I Have a Turn?題名: Can I Have a Turn?著者 : Norm Feuti出版社: ScholasticYL: 0.8語数: 592あらすじこの本には三つのお話が収録されています。そのうちの一つでは、ハリーが新しく手に入れた車のおもちゃをヘッジホッグに見せる場面が描かれます。ハリーは、その車がどんなふうに動くのか、どんなことができるのかを夢中になって説明します。するとヘッジホッグは「貸してほしい」と頼みますが、ハリーはなかなか手放すことができません。何度か待つうちに、ヘッジホッグは諦めて本を読み始めてしまいます。(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts;(b.q=b.q||,e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?2022...