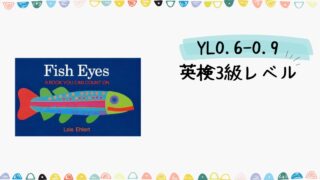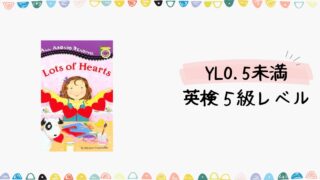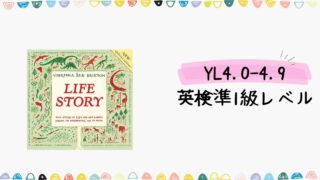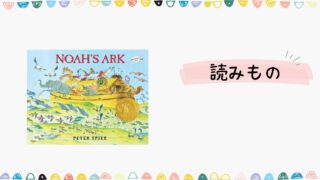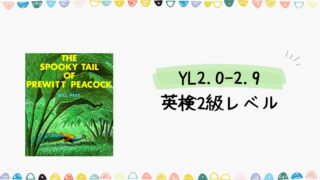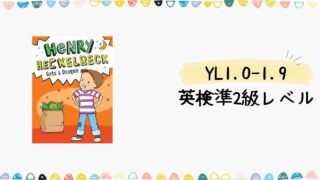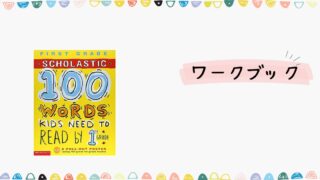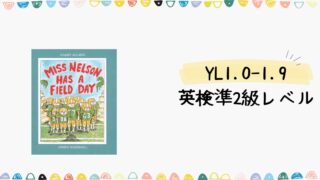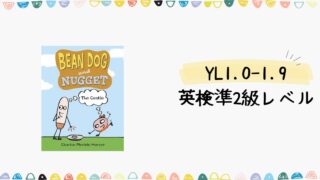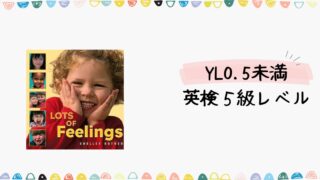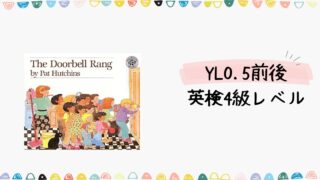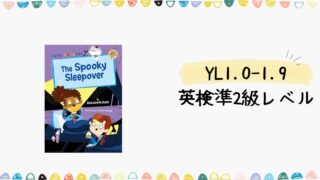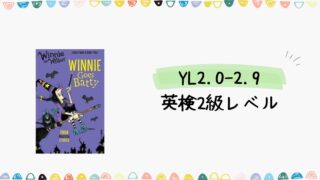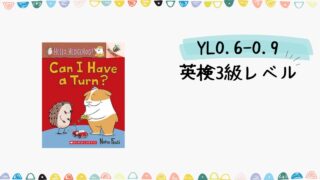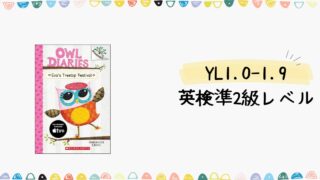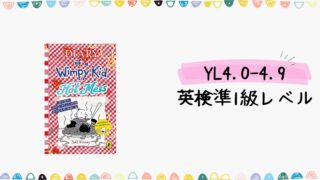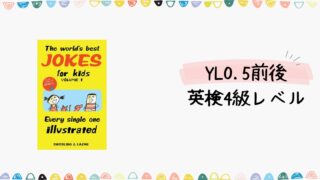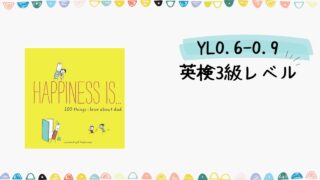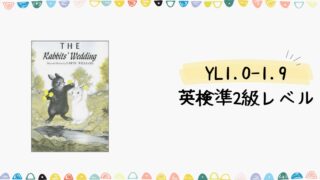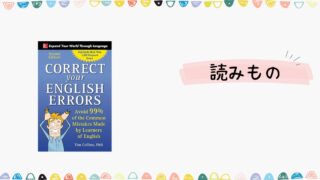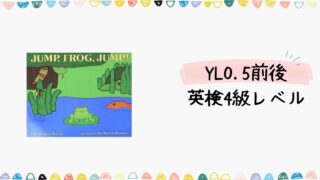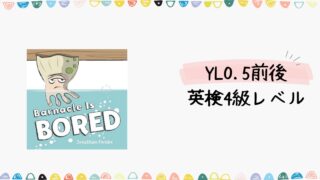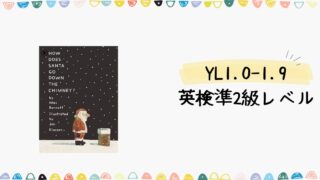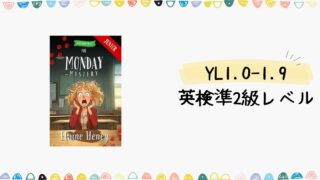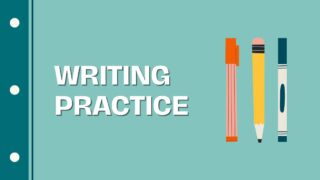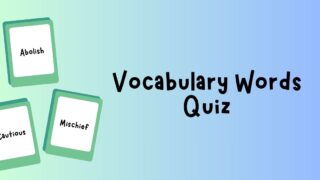- 多読は「読む力」=「使える英語力」の土台
- 英語多読で順調にレベルを上げていくには?
- 小学生:月10万語を超えるということ
- 中学生:月10万語を超えるということ
- 中学生で1万語未満の読了語数だと?
- 「月1万語」と「月10万語」の比較
- 中学で読んだ人と読まない人の差は?
- 成果の「質的転換点」は月3〜5万語
- 学習者の言葉でたとえると…
- 差が生まれる理由
- 高校で10万語を切る場合は?
- 高校生・月間語数別 目安と伸び方の違い
- 高校生:月間読了5万未満と10万以上の違い
- 高校生:月5万語未満 vs 月10万語超え 比較
- 「知識で覚えた英語」vs「経験で身につけた英語」
- 多読から離れてしまう「負のスパイラル」の典型パターン
- 多読は「静かな革命」
多読は「読む力」=「使える英語力」の土台
多読とは、「自分にとって易しい英語をたくさん読むこと」です。
語数は、英語力の成長を可視化する大きな指標であり、
「どれだけ英語に触れたか」「どの段階にいるか」が明確になります。
英語多読で順調にレベルを上げていくには?
多読で順調にレベルを上げていくために必要な「月間語数(words/month)」は
学年や英語力の段階によって変わりますが、
一般的な目安を書きました。
小学生
| 学年 | 目標語数(月) | 解説 |
|---|---|---|
| 小1〜小2 | 3,000〜5,000語 | 絵本中心。音読や読み聞かせが中心。自分で読む経験を増やす段階。 |
| 小3〜小4 | 5,000〜10,000語 | 短いストーリーを一人で読む練習。多読習慣がついてくる。 |
| 小5〜小6 | 10,000〜20,000語 | シリーズ物のリーダーに挑戦できるレベル。YL0.6〜1.2程度。 |
中学生
| 学年 | 目標語数(月) | 解説 |
|---|---|---|
| 中1 | 20,000〜30,000語 | 毎日読書の習慣がつくと急に伸びる。YL1.0〜1.5程度を中心に。 |
| 中2 | 30,000〜50,000語 | 語数も内容もステップアップ。Graded Readersに入る時期。 |
| 中3 | 50,000〜70,000語 | YL1.5〜2.5に挑戦。英検準2の語彙カバー率が上がってくる。 |
高校生
| 学年 | 目標語数(月) | 解説 |
|---|---|---|
| 高1 | 70,000〜100,000語 | YL2.5〜3.5程度。ネイティブ向けの簡単な本にもチャレンジ。 |
| 高2 | 100,000〜150,000語 | YL3.5〜4.5。長めの本をじっくり読む練習を。語彙力が伸びやすい時期。 |
| 高3 | 150,000語以上 | YL5.0以上も視野に。語数よりも内容重視・自分の興味で選ぶ。 |
補足ポイント(共通)
- 読書時間:1日20〜30分でも、月に1万〜3万語は可能です
- 一気に無理するより「習慣化+継続」が最重要です
- 月10万語を超えると、かなり語彙・読解力が伸びます

小学生:月10万語を超えるということ
小5・小6で月に10万語以上読むお子さんは、
英語歴・読書習慣・理解力のいずれにおいても非常に高いレベルにあると考えられます。
そのようなお子さんの特徴と目安となるリーディングレベル
小学生で月10万語を超える子のレベルとは?
英語力の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CEFR換算 | A2〜B1(例:英検準2級〜2級)レベル相当 |
| YL(読みやすさ) | YL1.5〜3.0程度の本をスラスラ読める |
| 語彙レベル | 約2,000語〜3,000語以上の基本語彙が定着 |
| 英文の処理速度 | 意味を訳さずに「英語のまま」理解し始めている |
読書スタイルの特徴
- 英語を英語のまま受け取る「英語脳」が育っている
- わからない単語があっても前後関係から推測する力がある
- 辞書なしでも読書が可能(辞書を引く回数が非常に少ない)
- 多読が習慣化していて、読みたい本が自分で選べる
- ストーリーや感情の流れを日本語に訳さず理解できる
保護者・指導者が気をつけたいポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 興味のあるジャンルを尊重 | 量は足りているので、「何を読むか」が鍵になる |
| アウトプットを促す | 書く・話す活動とセットにすると語彙が定着しやすい |
| 英語で考える力の強化 | 英英辞典や簡単な要約活動にもチャレンジ可能 |
| 日本語とつなぐ読書も大切 | 好奇心の源は日本語の世界。並行読書もおすすめ |
中学生:月10万語を超えるということ
中学生で月10万語を読了する
中学生で月に10万語以上読むというのは、全国的に見てもかなりハイレベルな読書量です。
これは英語学習としても、言語習得としても非常に理想的なペースであり、
英語力を飛躍的に伸ばせる状態にあります。
中学生で月10万語以上読む生徒のレベルとは?
英語力の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CEFR換算 | B1〜B2(英検2級〜準1級レベル)相当 |
| YL(読みやすさレベル) | YL2.5〜4.0の本をスラスラ読める |
| 語彙力 | 約3,000〜5,000語の英語語彙が定着している |
| 読解の自立性 | 読書に辞書をほとんど使わない/使わなくても理解できる |
学習・読書スタイルの特徴
- 英文を頭から処理し、訳さずに理解している(英語回路ができている)
- ジャンルやシリーズにこだわらず、自分の興味に沿って本を選んでいる
- 知識や表現がスピーキング・ライティングにも応用されてくる
- 読書の中で、語順・冠詞・語感が自然に身についている
この時期に意識したいステップアップ
| スキル | 具体的な活動 |
|---|---|
| スピーキング | 多読で得た表現を使って自分の意見を言う(Book Talk, 要約など) |
| ライティング | アカデミックライティングを学ぶ |
| リーディング | フィクション+ノンフィクションをバランスよく読む |
| 認知の発展 | 英英辞典を活用し、単語のニュアンスを英語で理解していく |
中学生で1万語未満の読了語数だと?
中学生で月に1万語未満という読書量は、
多読の視点から見るとまだスタート段階か、停滞期にある状態です。
ただし、これは「悪い」というより、どこに課題があるかを見極めるチャンスです。
レベル感・語彙力の目安(多読語数1万未満)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CEFR目安 | A1〜ごく初期A2(英検4級〜3級)程度 |
| YL | YL0.5〜1.0程度の本に触れている可能性が高い |
| 語彙数 | 約800〜1,000語前後が定着している段階 |
| 特徴 | 「訳す」習慣が強く、英語を英語のまま処理するにはまだ負荷が高い |
「月1万語」と「月10万語」の比較
中学生で月間多読語数が 「1万語」と「10万語」では、 見た目以上に大きな差が生まれます。
単なる「語数の9倍差」ではなく、
脳の処理スピード
語彙の定着
英語回路の形成において、
決定的な質的な違いが育っていく年齢です。
| 観点 | 月1万語 | 月10万語 |
|---|---|---|
| 英語処理能力 | 英語を「読む」ことにまだ負荷あり。意味処理に時間がかかる | 英語を頭から自然に理解できる。訳さずに理解可能 |
| 読解スピード | 遅い。精読に近い | 速い。多読型のリズムで読める |
| 語彙の定着 | 目にする語が少なく、定着まで時間がかかる | 同じ語に何度も出会い、使える語彙が自然に増える |
| アウトプット力 | 書く・話すときに言葉が出てこないことが多い | 多読から拾った表現を自然に使えるようになる |
| 本のジャンル | 簡単な絵本や短編中心(YL0.6〜1.2) | 長めのストーリー、シリーズ物に移行(YL1.8〜3.0) |
| 英語への感情 | 「ちょっと大変だけど頑張るもの」 | 「面白い」「もっと読みたい」という快感がある |
中学で読んだ人と読まない人の差は?
中学時代に多読をした人としなかった人の差は、
短期的には見えにくいですが、
高校・大学・その後の英語力においては圧倒的な違いとして現れます。
中学生で「多読した人」と「しなかった人」の違い
| 観点 | 多読した人 | 多読しなかった人 |
|---|---|---|
| 語彙力 | 文脈の中で自然に覚えるので、語彙の定着が速く深い | 単語帳に頼りがち。意味は覚えても使えないことが多い |
| 読解力 | 文構造や語順に慣れ、速く正確に読める | 読むのに時間がかかり、訳読に頼る傾向が残る |
| アウトプット力 | インプットが豊富なので、話す・書くときに使える語彙・表現が多い | 英作文やスピーキングで言葉が出てこない |
| 思考力・表現力 | 英語で「考える」力がついてくる。文章の組み立てが上手くなる | 日本語で考えて直訳しがち。表現がぎこちない |
| 英語に対する姿勢 | 「英語=楽しい」「知識の入り口」として前向き | 「英語=科目」「覚えるもの」として消極的になりやすい |
成果の「質的転換点」は月3〜5万語
- 1万語レベルでは、「読むことに慣れる」段階
- 3〜5万語を超えると、「意味で読める」感覚が育ち始め
- 10万語を超えると、「英語が頭に流れる」状態になる
→つまり10万語は「質的転換の後の世界」で、吸収力が大きく変わります。
学習者の言葉でたとえると…
| 月1万語の生徒の感覚 | 月10万語の生徒の感覚 |
|---|---|
| 「意味は分かるけど時間がかかる」 | 「意味が自然に入ってくる」 |
| 「英語の本は疲れる」 | 「ストーリーが気になって読み進めてしまう」 |
| 「習った単語は見たことあるけど、すぐ忘れる」 | 「よく出てくる単語だから使えるようになった」 |
差が生まれる理由
- インプット量が違う → 遭遇する表現・構文・文型の数が違う
- 反復回数が違う → 同じ語彙を何度も見て「語感」が育つ
- 処理速度が違う → 頭の中の英語処理が速くなる(いわゆる「英語脳」)
つまり、10万語を読む人は、読むたびに
英語を使える力がどんどん育っているのです。

高校で10万語を切る場合は?
多読の習慣がない/読む時間が取れていない
レベル感
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CEFR目安 | A2〜B1(英検準2級〜2級)レベル |
| 語彙力 | 2,500〜4,000語程度は理解可能 |
| 読みやすさの上限 | YL2.0〜3.5程度も読めるが、読むスピードが遅い/量が少ない |
| 課題 | 「語数の壁を越える体験」がないため、伸びにくい状態 |
アドバイス
- 同じシリーズを連続して読むと読むスピードが上がる
- 1日15分〜20分でもいいので、日課にする工夫(学校の朝読など)が効果的
- 短編小説やノンフィクション系で興味喚起するのも有効
- 週ごとに語数目標を決めることで、目標意識が強化される
高校生・月間語数別 目安と伸び方の違い
| 月間語数 | 読書習慣のレベル | 成果の出方 |
|---|---|---|
| 〜3万語 | 入門/習慣化前段階 | 英語に対する抵抗が少なくなる。読む楽しさに出会える段階 |
| 3〜7万語 | 習慣化の途中 | 文構造や語順のパターン認識が始まる。英語で考える力がつく |
| 10万語以上 | 自立型多読 | 思考や表現の力まで発展。CEFR B1〜B2へとつながる力に |
高校生:月間読了5万未満と10万以上の違い
高校生で「月5万語未満」と「月10万語超え」の読書量の違いは、
高校英語の土台の質をどう築くかという意味で、極めて大きな差を生みます。
この時期は、英語の「量」から「質」への転換点。
多読量によって、英語力の成長スピードと深さに圧倒的な違いが出てきます。
高校生:月5万語未満 vs 月10万語超え 比較
| 観点 | 月5万語未満 | 月10万語超え |
|---|---|---|
| 読解スピード | 遅め。訳読傾向が残る | 速く・頭から英語で読める |
| 処理の深さ | 表面理解が中心。文構造でつまずきやすい | 抽象・論理構造も自然に処理できる |
| 語彙定着 | テスト語彙は覚えるが使えない | 文脈の中で繰り返し出会い、使える語彙に |
| 英作文力 | 書けるが型通り・表現が乏しい | 自分の言葉で柔軟に書けるように |
| スピーキング | 単語が出てこない・不安定 | 読んだ語彙を使ってスムーズに話せることが増える |
| 英語への姿勢 | 「できる人が頑張るもの」 | 「自分も成長できるツール」へ |

「知識で覚えた英語」vs「経験で身につけた英語」
「問題集中心」の中学生と、
「多読を順調に積み重ねた中学生」では、
最終的な英語力の質と伸び方がまったく異なります。
| 観点 | 問題集中心の中学生 | 多読中心の中学生 |
|---|---|---|
| 英文理解 | 文法を当てはめて読む/単語を訳して読む | 意味の流れで読む/訳さずに頭から理解 |
| 語彙力 | 単語帳で覚える → 忘れやすい | 文脈の中で出会う → 使える語彙として定着 |
| 英作文 | 習ったパターンは使えるが応用が苦手 | 表現の幅が広く、自分の言葉で書ける |
| スピーキング | 習ったフレーズを思い出す → 詰まりやすい | 多読から拾った自然な表現が口に出やすい |
| リスニング | 単語単位で聞いて理解が追いつかない | 文全体を「意味のかたまり」として聞ける |
| 英語への感情 | 「正解しなきゃ」「暗記しなきゃ」で疲れやすい | 「面白い」「もっと読みたい」で自発性が高い |
多読から離れてしまう「負のスパイラル」の典型パターン
① 多読量が少ない
↓
② 伸びを実感できない(点数が上がらない)
↓
③ 不安になり、文法や単語に重点を移す(問題集へ)
↓
④ 多読の時間がますます減る
↓
⑤ 英文は訳さないと読めない → 英語回路が育たない
↓
⑥ リスニングが「別物」に見えてしまい、ますます伸び悩む
↓
⑦ テストで点数が下がる or 伸びない
↓
⑧ 「やっぱり多読は向いてなかった」と結論づけてしまうなぜこのスパイラルに陥るのか?
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| ❌ 短期間で成果を求めすぎる | 多読は“水やり”。効果が出るのに時間がかかる |
| ❌ 語数だけを指標にしすぎる | 1冊を「意味で読む」経験が少ないと、ただの文字の羅列になる |
| ❌ インプットとテスト勉強を別物と捉える | 問題演習とインプットのバランスを誤ると、効果が見えにくくなる |
| ❌ リスニングを“勉強”と切り離す | 本来、リーディングとリスニングは同じ英語回路で処理されるべきもの |
英語力の好循環
「簡単な英語をたくさん読む」
→「意味で読めるようになる」
→「聞こえる/書ける/話せる」
→「英語のまま理解できるようになる」
→「テストの英文も怖くない!」
多読は「静かな革命」
多読はすぐに成果が見える学習ではありません。
でも、「わかる」「読める」「もっと読みたい」と思えたとき、
その人の英語力は“内側から育ち始めて”います。
焦らず、止めず、比べず、続けましょう。