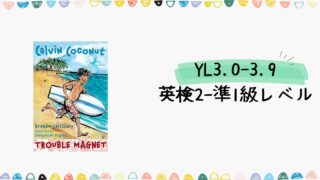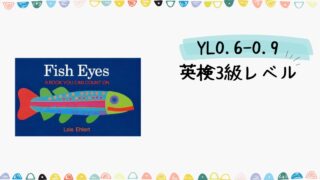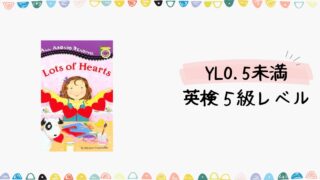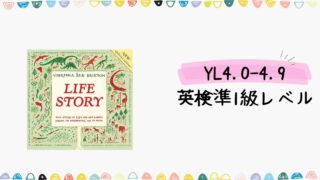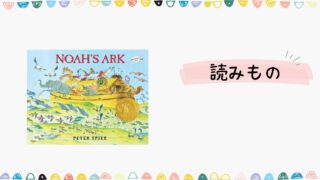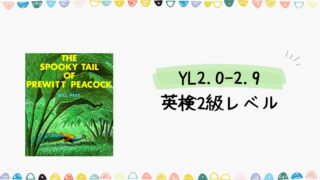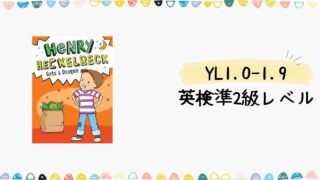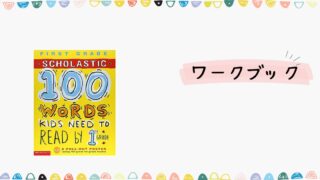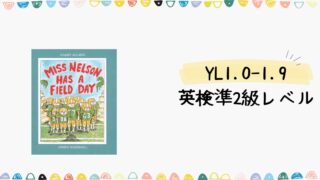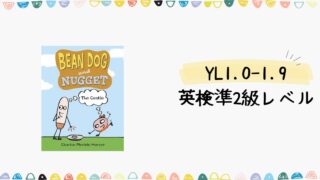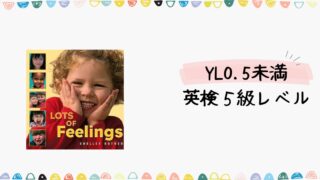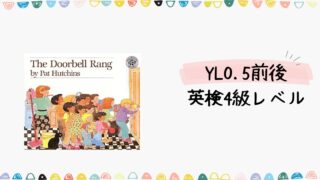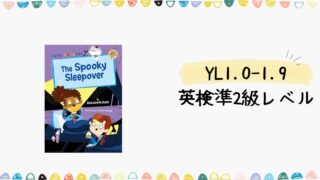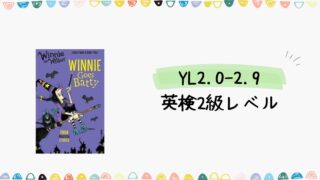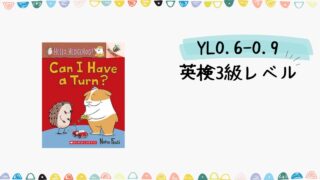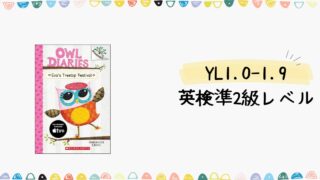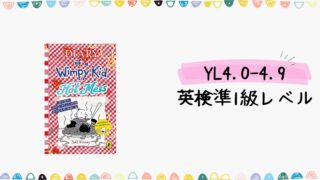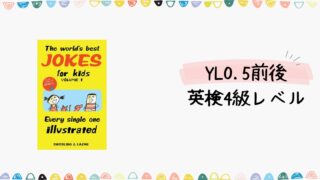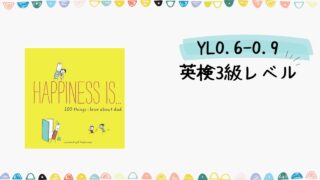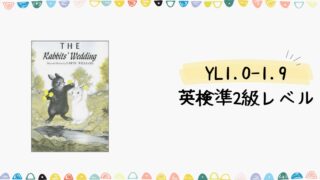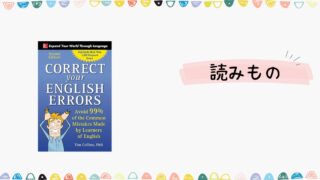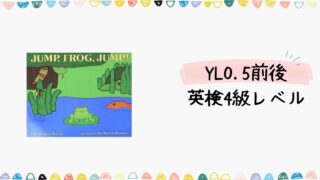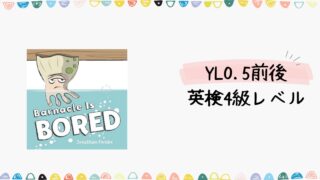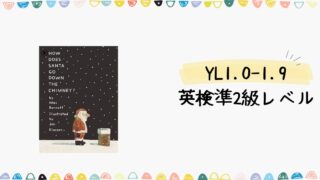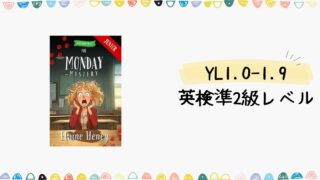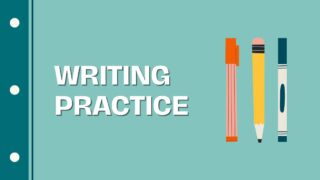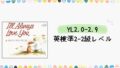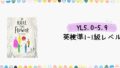文法が微妙
文法が苦手な生徒は、昔から今も、そしてきっとこれからも存在します。
興味深いのは、そうした生徒の多くが「真面目で、英語が得意」と思われていることです。
リスニングや語彙力が高く、
テストでもある程度の点数が取れてしまう。
英語を話すこともできる。
だから周囲からは「英語ができる子」と見なされがちです。
けれど、
いざ文章を書かせたり、
英語で話してもらうと、
文法力の弱さがあらわになります。
そして「超」高得点にはなかなか届かない。
細かいミスを自覚しないまま、少しずつ失点しているからです。
私はこの現象に長年悩んできました。
「多読のせいなのか?」と考えたこともありますが、それは違いました。
外部から来た塾通いの生徒たちも同様に、文法が崩れている。
むしろ、多読をしていない生徒の方がさらに厳しい状況でした。
そしてようやく得た結論があります。
それは——「流してしまう意識」が原因だったのです。
「文法は後回し」という癖
英語が得意と自他共に思っているけど、実は文法が苦手な生徒の多くには、「文法を後回しにする」癖がついています。
それでもある程度点が取れるため、間違ったまま定着してしまうのです。
そして多くの場合、彼らは自分が文法を本当に苦手としていることにまだ気づいていません。
「文法苦手なんだよね〜」と言っている生徒も、
実際にはそれを「直したい」とは思っていない。
つまり、本当の意味で気づいてはいないのです。
文法が定着しない子どもに見られる行動パターン
- 読んでいても「だいたい分かるからいいや」と流してしまう
- 「文法が分からなくても点は取れる」と軽視する
- 文法ミスを指摘されても「えへへ」と笑って済ませてしまう
- 日本語をそのまま英語に置き換えて「書けた」と思い込む
- 「文法が苦手だね」と伝えると、「どうしたらいいですか?」と“教えてもらう前提”で返してくる
文法は「自分で気づく」ことでしか変わらない
他人に「ここが間違っているよ」と言われても、
受け入れる準備ができていなければ何も変わりません。
文法というのは、自分の中で
- 「これはおかしい」と気づく力
- 「直したい」と思う意志
この内側の力=内発的動機がなければ伸びにくい分野なのです。

文法が苦手かどうかは、英検準1級で明確になる
私は英検を重視しているわけではないですが、長年生徒たちを見ていて、
文法力がぐらぐらだと英検準1級が届かない子が多い
と肌で感じています。
英検2級までは、「意味が通じればOK」という評価基準で乗り切れてしまいます。
多少文法ミスがあっても、語彙や構成でカバーできてしまうからです。
しかし、準1級になると状況は変わります。
- アカデミックな文章の読解では、複雑な構文を正確に読み取る力が必要
- ライティングでは、複文や論理的接続が自然で正確に使えるかどうかが問われる
- 内容が豊かでも、文法が破綻していれば評価は大きく下がる
つまり、「文法を使いこなせる力」=構文力・制御力が問われるのが準1級以降なのです。
英語力の土台は「音・文法・語彙」の三本柱
どれか一つ欠けても、英語は「聞けない」「話せない」「読めない」「書けない」につながります。
英語力を家にたとえるとこうです:
- 語彙は建材(材料)
- 文法は設計図(構造)
- 音は基礎(土台)
どれかが欠ければ、崩れやすい・伝わらない・伸びにくい英語力になります。
さらにこの三本柱は、
- 「理解して学ぶ」プロセス
- 「慣れて自然化させる」プロセス
の両方が必要です。
わからないことをわかるようにしてくれるのは、先生や教材かもしれません。
でも——
「できるようにする」のは、自分しかいません。
I like apple. という例がすべてを物語っている
名詞 apple に冠詞や複数形が必要なことは、誰でも教わります。
でも、「通じればいいや」というスタンスのままではI like apple.
という不自然な文を、いつまでも「正しい」と思って使い続けてしまうのです。
これは、「指導の問題」ではありません。
「本人の姿勢と意識」の問題なのです。
最後に
文法の力は、誰かが与えてくれるものではありません。
「自分で直したい」
「うまくなりたい」
と心から思ったとき、初めて変わり始めます。
学びの核心は、
「教えてもらうこと」ではなく、
「自分が変わりたいという気持ち」です。
そして私は、
英語を本当に使いこなせるようになりたいと願う中高生たちが、
できるだけ早い段階で文法の重要性に気づき、
真剣に向き合ってくれることを、心から願っています。