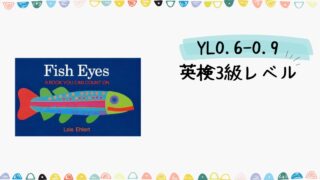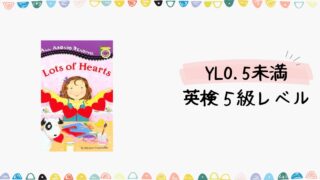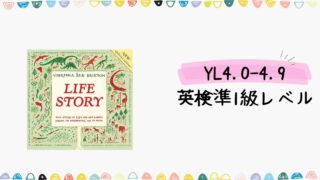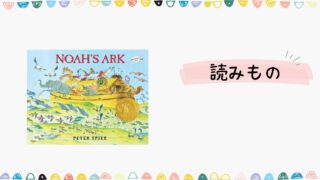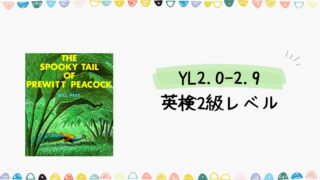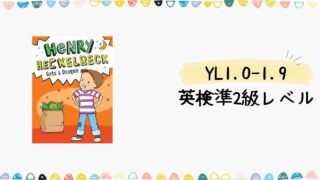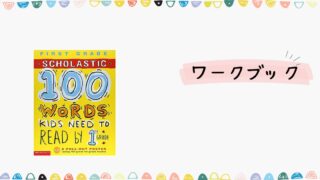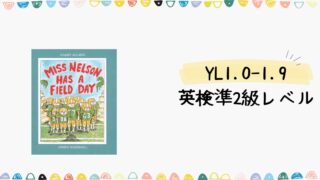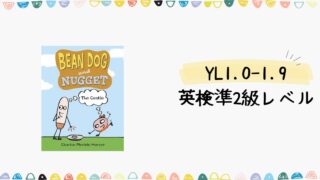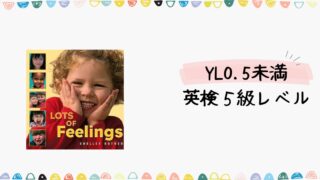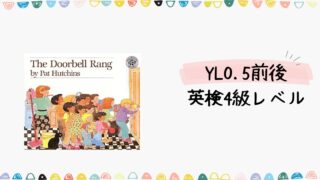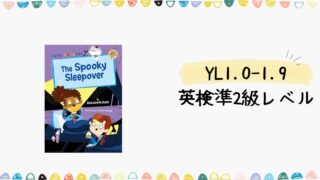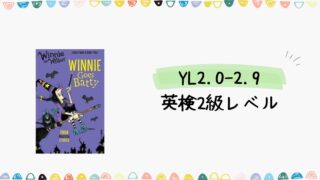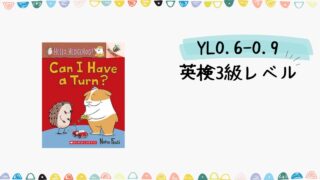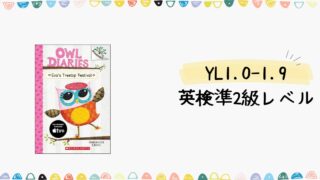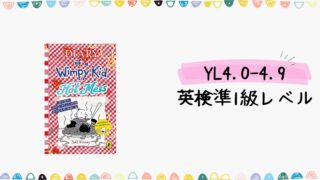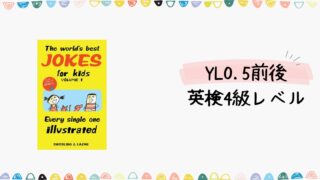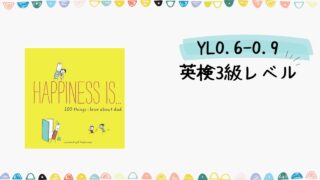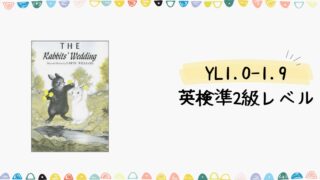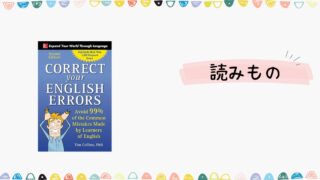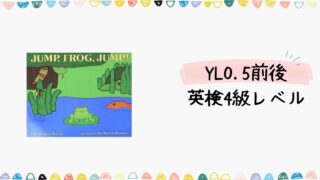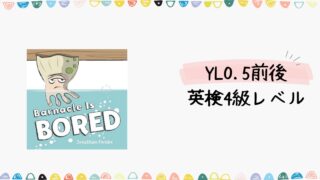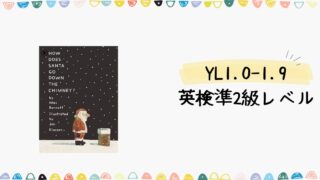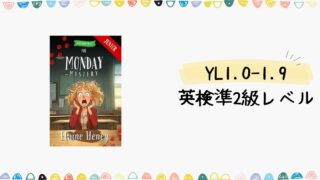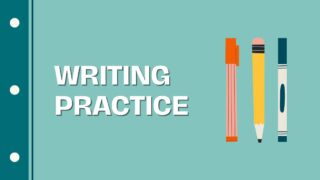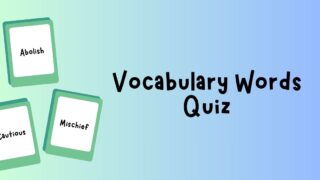高校生で月10万語に届かない場合、表面的な問題だけでなく
深い部分での「伸びの限界」が起きてきます。
高校生で月10万語に届かないと起きやすい問題
読解スピードの頭打ち
- 単語や構文を逐語的に処理する読み方から抜け出せない
- 長文を読むのに時間がかかり、試験時間に間に合わない
- 精読ばかりになり、内容把握より訳に意識が向く
月10万語に届くと:「意味のかたまり」で理解 → 直読直解が可能に
語彙の「使える化」が進まない
- 単語帳で覚えた語彙が文脈で出てきても認識できない
- 自分で使うときに語彙が口から/手から出てこない
- 結果、英作文やスピーキングに表現の幅が出ない
月10万語に届くと:文中で繰り返し出会う語彙が「使える語彙」になる
リスニングとの連動が弱い
- 読み慣れていない構文・語順は聞いても処理できない
- 英語の音が意味につながらず、単語拾いのリスニングに終始
- 結果:リスニング力の伸びが頭打ちになりやすい
多読量が増えると:リスニングでも意味単位で理解できるようになる
英語で考える力が育ちにくい
- 論理的な文章・抽象的な内容に頭がついていかない
- 意見を求められても、語彙や構文に頼りきりで薄い表現に
- 英語を「考える道具」ではなく「暗記と処理の科目」として見てしまう
月10万語を超えると:読みながら考える・読んだ上で意見を持つことが可能になる

月10万語に届かない場合の本質的なリスク
| 項目 | 問題 |
|---|---|
| 処理スピード | 試験や実用場面で対応できない |
| 語彙の運用力 | 単語は知っているのに使えない |
| 読解の質 | 精読止まり。論理構造が見えにくい |
| 思考力・表現力 | 「自分の考えを英語で組み立てる」段階に届かない |
| 英語への姿勢 | 英語=覚えるもの/テスト対策になりがち |
すぐ10万語が無理でも…
- まずは 月5万語 → 7万語 → 10万語へ と段階的に増やす
- 興味ある分野のリーダーや小説を選ぶと、語数は自然に伸びます
- 「毎日20分以上読む」が10万語への安定ルートです
中学生だと月10万語読めば「全国的に高いレベル」なのに高校になると10万語は最低ラインとなるのはなぜか?
中学生で月10万語=高レベル、なのに
高校生で月10万語=ようやく基礎ライン。
この逆転現象は、英語そのものというより、
英語に求められる「役割の違い」によって生まれます。
なぜ高校では「10万語が最低ライン」になるのか?
英語の「目的」が変わるから
| 学年 | 英語の主な役割 |
|---|---|
| 中学生 | 読むことに慣れる・語順に慣れる・構文に触れる |
| 高校生 | 論理的に読む・自分の考えを表現する・英語で学ぶ |
→ 中学生では「量をこなすだけでも高い力」
→ 高校では「それを使って考える」「表現する」ステージに進む
テキストの難易度・要求される理解の深さが違うから
| 比較 | 中学生 | 高校生 |
|---|---|---|
| 文長 | 短め(100〜300語) | 長め(500〜1500語) |
| 語彙 | 基本動詞+日常語彙 | 抽象語・論説語彙が増加 |
| 内容 | 描写中心/具体的 | 主張・比較・因果・抽象概念など論理性重視 |
| 読み方 | 表面理解(What) | 筆者の意図・理由(Why)/批判的読解(How) |
→ 高校生には「読む深さ・処理スピード・判断力」が同時に求められる
→ 月10万語はそれらの下支えになる“最低限の慣れ”を作る語数
「頭の英語回路」が完成に向かう段階だから
- 中学生:まだ日本語⇄英語を行き来する段階
- 高校生:英語を英語のまま保持・処理できる脳の回路を作る時期
→ 多読が“英語を処理する脳内ワーキングメモリ”を強化する
→ 月10万語を超えなければ、情報が保持できず読解が浅くなる
たとえるなら…
中学生で月10万語は「高地トレーニング」
(周囲より一歩進んだ環境で走っている)高校生で月10万語は「ようやく酸素が足りる標高」
(10万語読まないと、まともに英語で走り続けられない)
中学生で月10万語は「習得フェーズの上位」
高校生で月10万語は「活用フェーズの入り口」
中学の多読と高校の多読は全く別物なのです
中学の多読と高校の多読は、
見た目が同じ「英語を読む」でも、目的も内容も求められる力も「全く別物」です。
これはとても重要なポイントで、指導者・保護者・学習者本人にとっても認識の転換が必要です。
中学の多読 vs 高校の多読の本質的な違い
| 項目 | 中学の多読 | 高校の多読 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 英語に慣れる/語順・構文に触れる | 英語で思考する/深く理解・表現する |
| 読書スタイル | 易しい本をテンポよくたくさん読む | 複雑な内容も理解しつつ読み進める |
| 処理の特徴 | 語順・意味を英語のまま保持する回路を育てる段階 | すでに育った回路を「使いこなす」段階 |
| アウトプット | シンプルな感想・要約・音読 | 要約・意見・英作文・スピーキングへの応用 |
| 英語との関係性 | 「読める喜びを感じる」 | 「英語で何かを理解し、考え、伝える」 |
たとえるなら…
- 中学の多読は、英語という「道」を作る作業
→ 語順・語彙・構文に慣れ、読める基盤を整える - 高校の多読は、その「道」を使ってどこかへ「行く」作業
→ 論理を読み解き、考え、英語で理解を深めていく
重要な指導ポイント
| 誤解されやすい点 | 正しく理解すると… |
|---|---|
| 「高校でもとにかく読みやすい本をたくさん読めばいい」 | 高校では“内容的に負荷のある本”も必要(論理・批評・情報系など) |
| 「中学の延長線として語数を増やせばよい」 | 語数+“読む深さ”の両方が問われるようになる |
| 「語数が足りなくても精読で補える」 | 精読だけでは処理スピードが追いつかず、長文やリスニングに対応できない |
フェーズの違い
中学の多読=「読む力を育てる」
高校の多読=「読む力を使いこなす」
まったく別の目的を持った「学びのフェーズ」なのです。
小中学生でたくさん読んだからといって、高校まで安心…ではありません。
小中学生のうちに英語をたくさん読んでおくと、
語順や構文に自然に慣れ、英語をスムーズに理解できるようになります。
これは大きなアドバンテージです。
でも――
高校になると、英語に求められる力がガラッと変わります。
- 長くて複雑な英文
- 論理的な構成や抽象的なテーマ
- 英語で考え、自分の意見を述べる力
こうした力を身につけるには、中学まで以上に「たくさん読むこと」が必要不可欠です。
*小中学生の多読:英語に慣れる・読む力を育てる
*高校生の多読:英語で考える・深く理解する・使いこなす
つまり、小中学生のときの努力を「活かすため」にも、
高校ではさらに読む量と質をステップアップさせることが大切なのです。
だからこそ、小学生の時大して読んでない子が高校生でグンと伸びるのです
その理由はこちら↓
小中学生の「チンタラ多読」が高校で爆発的に伸びる理由
英語の“土壌”はすでにできている
- 少しずつでも多読を続けていれば、
→ 語順や構文への違和感がない
→ 英語に対する抵抗感がない
→ 辞書に頼りすぎない読解の土台がある
高校では「読む力を使う」学びに変わる
- 高校になると、英語で考える・読んで意見を持つなど、使うフェーズに突入します
- ここで多読のスイッチが入ると、
→ 急に読解スピードが上がる
→ 語彙が一気に“使える語彙”になる
→ 英作文やスピーキングにも波及
だから「読み方が変わった瞬間」が飛躍の合図
- 「チンタラ読んでいた子」が急に
「この本、英語なのに全部意味がわかる!」
「自分の考えも英語で浮かぶ!」
となったとき、そこからの成長は本当に早いです。