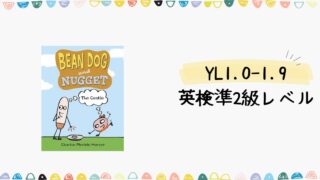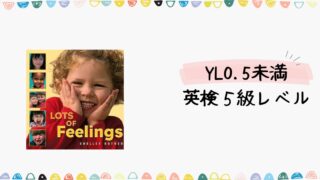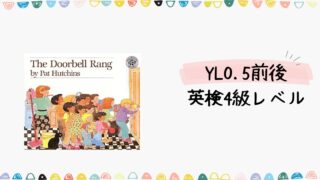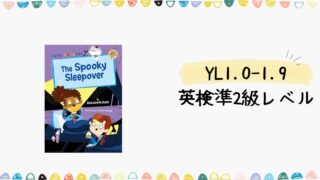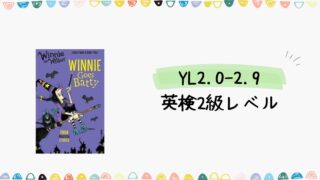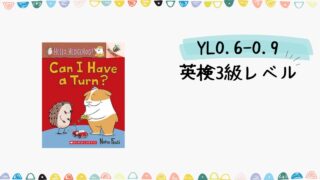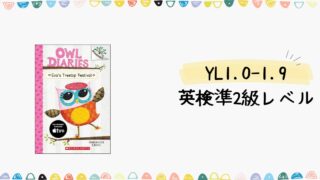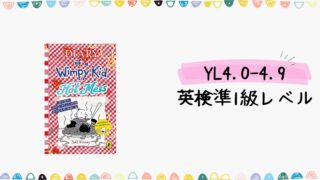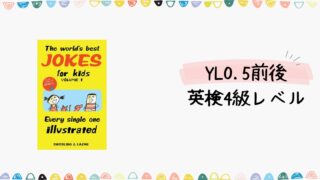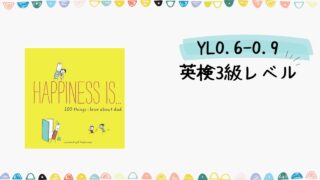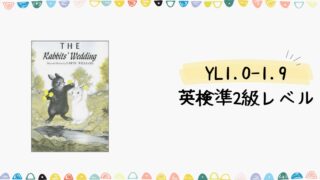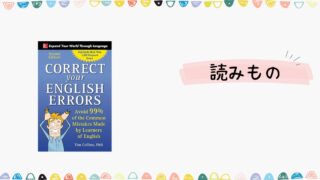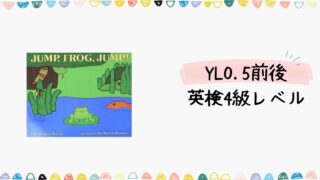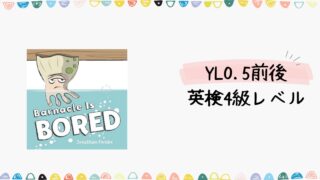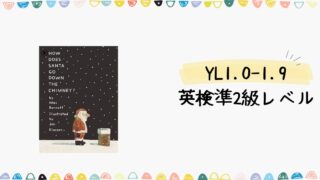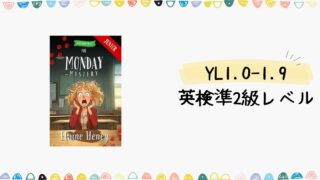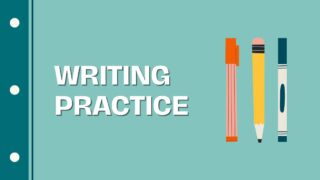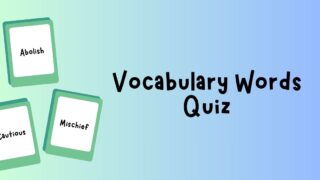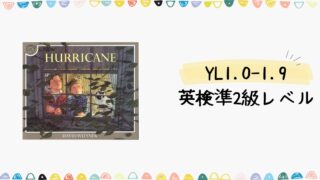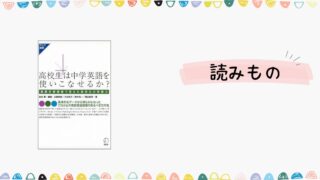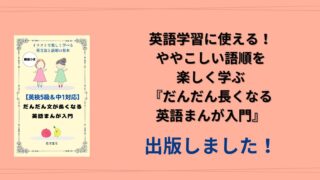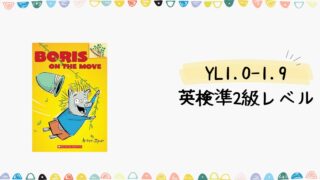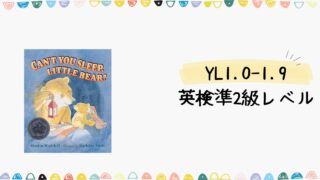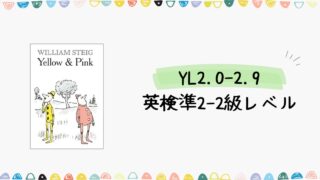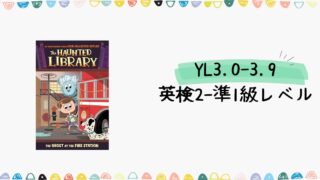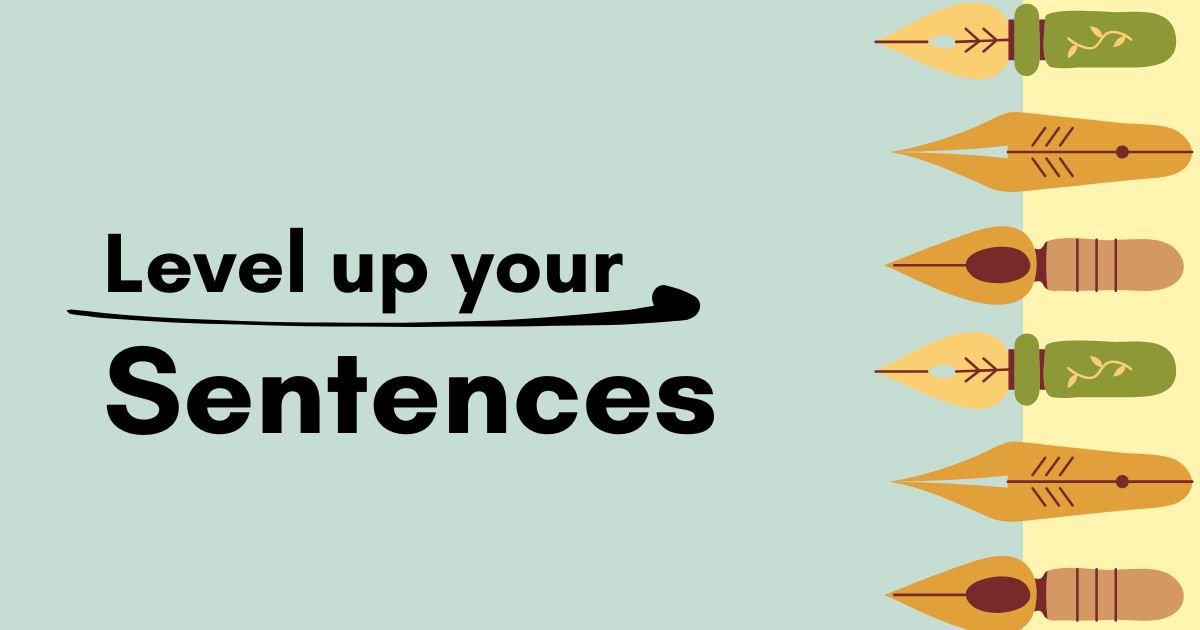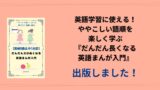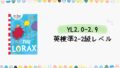語順という感覚
「語順が感じられない子」は努力不足ではない
真面目で、宿題もやり、多読もしている。
それでも語順が“ピンとこない”のは、
英語の入力(input)を「意味のかたまり」として処理できていないからです。
→ つまり、彼らの脳内では
say / to / your / mom / hello
のように「単語の羅列」として処理されており、
[say hello] [to your mom]
のような「chunk単位」での処理が起きていません。
「a」「the」が抜けるのは“チャンク処理ができていない”証拠
a sunny day → sunny day
のように冠詞を落とすのは、
その学習者の脳が「a sunny day」というひとかたまりをまだ認識していないためです。
心理言語学的には、これは「formulaic sequence(定型句)」が形成されていない状態。
母語話者は “a sunny day” を一語のように処理していますが、
学習者は “a / sunny / day” と3つの単語として処理している。
その結果、無意識に “a” を捨ててしまうんです。
これは冠詞の理解ではなく、視覚・音の処理の単位の違いです。
「on a sunny day in fall」を「in fall on a sunny day」とする理由
これもまさに「チャンク単位での構造把握」ができていない典型例です。
母語話者の感覚では:
[on a sunny day] [in fall]
という2つのブロックが並ぶ構造。
しかし語順が苦手な子は、語順を意味ではなく単語の順列で考えるため、
「in」も「on」も“時間の前置詞”として同列に処理してしまいます。
つまり、「どちらがどちらを修飾しているか」が見えていない。
これも “chunk blindness”(チャンクが見えない状態)です。
「多読本」や「問題集」ではカバーできない理由
- 多読本 → 意味をつかむ練習であり、構造を意識的に処理しない。
- 問題集 → 構造を説明するけれど、語順の流れ(chunk order)を感じる訓練にならない。
つまり、
“form-focused input” (構造を見せる入力)
が欠けている状態です。
研究的にも裏付けがあります
第二言語習得(SLA)の研究でも、
語順や構造(form)への注意が育たない理由は繰り返し指摘されています。
VanPatten(1996)は、学習者は言語を処理する際にまず「意味」に注意を向ける傾向があると述べ、
意味処理に集中しすぎると形(form)への注意が阻害されると説明しています。
つまり、多読やリスニングのように「意味理解中心」の活動では、
語順や構文パターンが自然に定着しにくいのです。
Ellis(2012)は、流暢さ(fluency)は単語の知識ではなく、
チャンクとして処理できる量と質によって決まると述べています。
Leow(2015)も、文法説明よりも構造の可視化が処理効率を高めると指摘しています。
これらの研究は、
多読や音読だけでは語順処理が自動化されにくい
文法指導だけでは感覚が育たない
ということを示しています。
英語の語順を「感じる」ためには、
意味理解中心の学習(多読)と構造を見せる学習(チャンク練習)の両輪が必要です。
【音読しても語順が身につかない理由】
音読もまた、どれだけ頑張っても語順が身につかない子がいます。
声に出して読んでいても、英語を“流れ”としてではなく、“単語の点”として処理してしまうからです。
一見流暢に読んでいても、頭の中では still say / to / your / mom / hello のようにバラバラに並んでいる場合があります。
意味を追うことに集中しすぎると、文の形や語順の流れへの注意が薄れてしまうのです(VanPatten, 1996)。
語順を感じ取るためには、どこで区切るか・どのかたまりで動いているかを意識して読む必要があります。
音読は素晴らしい練習ですが、単語を順に読むだけでは語順の感覚は育ちません。
英語の「流れ」をチャンクごとに感じ取る練習が欠かせません。
【多読をしても語順が身につかない理由】
多読も音読と同じで、量をこなしていても「語順の感覚」が身につかないことがあります。
英語を読むとき、脳はまず意味を理解しようとするため、
文の形(form)や語の並び方(order)に注意が向きにくいのです。
そのため、文章全体の内容はわかっても、
「なぜこの順番で言うのか」が感覚的にわからないまま進んでしまいます。
多読は「意味を大まかにつかむ力」を伸ばすにはとても効果的ですが、
「語順の型」や「英語の流れ」を体で感じる練習にはなりにくい学習法です。
語順を身につけるためには、文のかたまりを意識して読んだり、 チャンクごとに目で見える形で捉えることが大切です。
【文法を学んでも語順が身につかない理由】
文法をしっかり学んでも、語順が自然に使えるようになるとは限りません。
文法学習は「ルールを理解する」ことを目的としており、
「英語の流れを感じる」こととは別の力だからです。
たとえば三人称単数の s や時制の使い方は理解できても、
どの順番で単語を並べるかという感覚までは、文法説明だけでは身につきません。
文法は“理屈で説明できる力”を育てますが、語順感覚は“体で感じて自動化される力”。
その間には大きなギャップがあるのです。
ほとんどの子がそうじゃない??
はい。
「語順を感覚で捉えられない子」=実はほとんどの子どもたちです。
つまり、例外的に“できる子”がいるのであって、
“できない子”が多数派なんです。
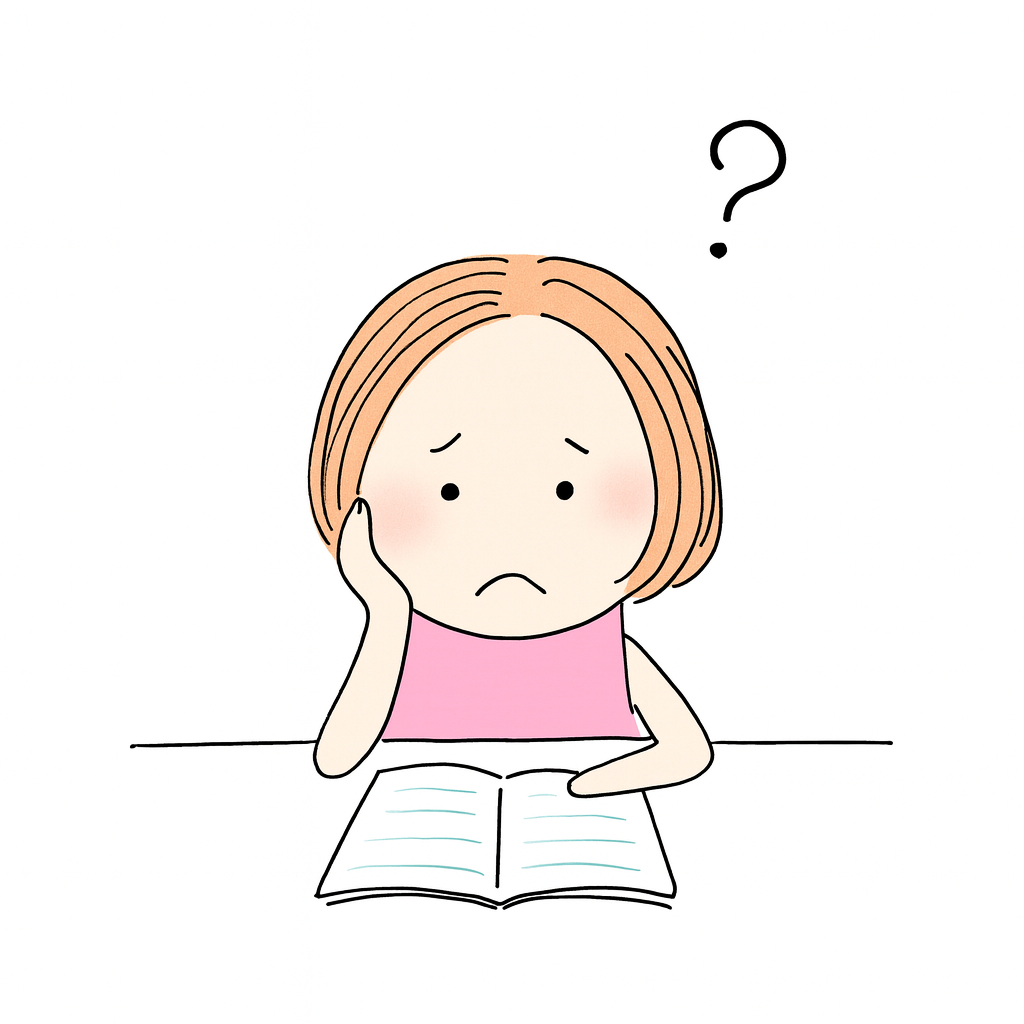
なぜほとんどの子が当てはまるのか
日本語は「後ろから前に」情報を組み立てる言語
日本語は「修飾語が前」「結論が後」という構造でできています。
- 英語:She met a friend at the station.(情報を右に足していく)
- 日本語:駅で友達に会った(情報を左に積み重ねる)
この構造差だけでも、英語の「左から右へ流れる感覚」を自然に身につけるのは非常に難しいんです。
学校英語では“文法”は教えるけど、“語順感覚”は教えない
文法は「説明できる」けれど、語順感覚は「体感する」しかありません。
ところが、従来の授業ではその「体感部分」がほとんど抜け落ちています。
生徒の頭の中: “I know what the rule says, but I can’t feel how it flows.”
語順を感覚でつかむには「視覚」「リズム」「反復」が必要
英語を「右に伸びる構造」として視覚的・聴覚的に体感する必要があります。
でも、ほとんどの子はその練習を体系的にやったことがない。
→ 結果的に、単語がバラバラに見える状態で止まってしまうんですね。
「多読」だけでは構造処理を自動化できない
多読は素晴らしいですが、目的が「意味理解」なので、
語順の処理を脳がスキップしてしまうことがあります。
多読 → 意味をつかむ力を育てる
チャンク練習 → 英語の構造を感じる力を育てる
両輪が必要なのに、現場では「多読」だけで十分と思われがちなんです。
高校で差がでる理由
高校英語で「差」が出るのは、
“できない子が増えた”のではなく、 “できる子だけが伸びていく”構造だからです。
中学までは「文法暗記」でなんとか回せても、
高校で抽象的な文・長文・多層構文になると、
「語順感覚」がない子は一気に壁にぶつかります。
【語順という落とし穴】
英語の語順は、学習が進めば進むほど見えにくくなる「落とし穴」です。
多読も音読も文法学習も、それぞれ大切な学習法ですが、 どれも「語順の感覚」を育てる練習にはなりにくいという共通点があります。
英語は「語順の言語」です。
だからこそ、語順を感覚でとらえられないまま上のレベルに進むと、 表面的には読めても、構造の理解や文の流れがつかめなくなります。
「意味はわかるけど、なんだかしっくりこない」という状態が続くのです。
この「語順の落とし穴」に気づかずに進むと、 高校で一気に理解が止まってしまうケースも少なくありません。(作文させればすぐわかります)
語順は、目に見えないけれど、英語の根っこにある“流れの感覚”です。
だからこそ、早い段階でチャンクとして見える形で意識させることが大切なんです。
(それも相当しつこく😅です…)